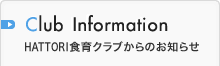食育に関する情報・食育の実践なら 【HATTORI食育クラブ】
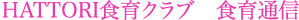 No.25
No.25
日本から発信する「味」だから「TOKYOTASTE」

中村 晴
キッコーマン株式会社 執行役員/
広報・IR部長
(写真左)
服部 幸應
服部栄養専門学校 校長/医学博士
(写真右)
キッコーマン株式会社 執行役員/
広報・IR部長
(写真左)
服部 幸應
服部栄養専門学校 校長/医学博士
(写真右)
- 服部
- 「世界料理サミット2009」の開催を思いついたきっかけは、2005年に世界の名だたるシェフの集まる「マドリッド・フュージョン」料理学会に招へいされた事です。スペインでは10年ほど前から開催されており、これはぜひとも日本でやらなければと思いました。 swiss replica watches
- 中村
- そのような経緯で、弊社会長の茂木が会長を務めさせていただいている「食文化研究推進懇談会」で服部先生がご提案されたのですね。
- 服部
- そうでしたね。日本のシェフや料理に興味がある方が彼らの技や料理を見ようと思うと世界中を廻らなければならない。一方で海外のシェフたちは、日本の食材にとても興味をもっているがなかなか目に触れる機会が少ない。そんな声を耳にすることがだんだん多くなり、これはぜひ日本で開催すべきだと思い食文化研究推進懇談会の2005年の報告書「日本食文化の推進」の行動宣言に盛り込んで頂きました。
- 中村
- ところで、昨年10月7日の世界料理サミットの記者会見で、最先端の調理技術のデモンストレーションを拝見しましたが、素晴らしいという以上に驚き、感心させられました。
- 服部
- これまでの料理というと伝統的な事をしていればよかった。伝統を守ることはもちろん大切なことですが、だんだんと料理も医療分野の技術も取り込み科学的になり、さらに盛り付けもファッショナブルな方向性を持ち始め、思いもよらない料理法が次々と考え出されています。
- 中村
- 料理の世界もお互いに刺激しあい新しいものを創りあげられているのですね。料理の世界にも大きな変革の潮流を感じます。
- 服部
- スペインの「エル・ブリ」のフェラン・アドリア氏は常に新しいことにチャレンジし、料理界のトレンドを創ってきました。例えば白いお皿を使う、いまでこそ誰でもがやっていることですが、彼が始めたことなのです。食の先端をいくフェラン氏は今回、海苔を使ったメニューを披露してくださる予定です。 www.gina-shop.com
- 中村
- 海苔をどう扱うんでしょう?きっと私たちが思いもよらないような使い方をするのでしょうね。とても楽しみです。
- 服部
- 他のシェフの方々も世界の料理界を牽引してきた方ばかりで、新しい技術や味を披露してくださるようです。ですから、西洋料理のシェフに限らず和食や中華料理のシェフの方々にも来て見て感じて欲しいです。きっとなにかインスピレーションを感じると思います。
- 中村
- 料理に携わる人はもちろん料理に興味がある人には料理を本やインターネットなどのバーチャルな体験だけではなく、料理を五感で感じて欲しいと考えています。ですから私も皆さんにはぜひ実際に目で見てほしいし、目の前で世界の最先端の料理を目に焼き付けることは一生の宝物にもなると思います。
- 服部
- 特に料理の世界に入ってきた若い人たちには見て欲しいですね。料理界のスーパースターたちの姿を実際に見ることで頑張れるエネルギーになるし、芸術の域に達したともいえる彼らの技や料理をみることは将来きっと役にたつと思いますよ。
- 中村
- 「世界料理サミット2009」で披露される調理技術や味がこれからのトレンドを作るわけですから、たくさんの人に来ていただきたいですね。最近の食の話題というと食の安全・安心の問題などネガティブな話題が多かったのですが、明るく素晴らしい情報を日本から世界に向けて発信できることは、とても有意義なことだと思います。
- 服部
- ヨーロッパ特にフランスではなかなか「うま味」が理解されていないように思います。フランス人たちがおいしいと感じているのは、脂肪分なんではないでしょうか。文化、食材の違いがあるのでしょうね。例えば、水質の違いも大きな要因じゃないかと考えています。多くのヨーロッパの水、硬水では鰹節で味は出るのですが、昆布の味はなかなか出ないんです。しかし、少しずつですが、研究熱心なシェフたちは日本の食材を含め、「だし」や「UMAMI」を料理に取り入れようとしています。「世界料理サミット2009」では食品メーカーや調理・厨房機器メーカーの展示会場を併設しています。この会場では改めて日本の食材を世界に正しくアピールできればと思っています。キッコーマンさんといえば、日本食がブームになる前から海外展開に力を入れてこられていましたね。外国のお店でお醤油を頼むとき、KIKKOMANと言わなければ出て来ないほどです。
- 中村
- ありがとうございます。確かにお醤油は日本の食材のなかでももっとも古くから海外に輸出されてきた調味料のようです。1737年に初めて東インド会社によってオランダに輸出されたという文献が残っていま す。
- 服部
- そんなに古い時代から輸出されていたとは驚きです。
- 中村
- また、1772年にフランスのディドロという啓蒙思想家が完成した世界初の「百科全書」に醤油の記述があり、骨付きハムにとてもよく合う素晴らしいソースであると紹介されているんです。キッコーマンも、1873年のウィーン万博、1883年のアムステルダム万博に出展、1900年のパリ万博では金杯を受賞しました。
- 服部
- 当時からヨーロッパの食文化にはお醤油が取り入れられていたんですね。
- 中村
- はい。いまではとても色々な使い方がされていて驚くことばかりです。「世界料理サミット2009」にも来られるロブション氏を20年前に弊社がお招きしたとき、作っていただいた料理に煮詰めた醤油がフレーバーとして使われていました。その料理は普段からお店で提供され、とても人気があるメニューなんだとお伺いし驚かされました。
- 服部
- いまはどれくらいの国で使われているんでしょうね。
- 中村
- キッコーマン醤油は、アメリカやヨーロッパのみならず、ロシアや中東諸国など世界100カ国以上で使われています。最近では日本食ブームも追い風になっています。それに伴って味噌やかつおぶし、昆布、のりといった食材も注目されてきているようです。
- 服部
- いまおっしゃられた食材以外にも日本にはとても素晴らしい食品や食材があります。海外にPRしていくためにはブランド力をつくり育てていかなければなりませんが、どうすればいいでしょうか。
- 中村
- 日本には、世界にあまり知られていない素晴らしい食材がまだまだあります。そうした食材を国全体が連携して守り育てていかなければいけないでしょうね。特にこれからの日本は少子高齢化が進むでしょうから海外輸出は重要な課題になると思います。きちんとしたルートを作ることが早急な課題ではないでしょうか?
- 服部
- 私たちは海外から入ってきたものをうまく加工して和洋折衷を作り上げてきました。しかし、いま、海外では日本の食材をうまく使った洋和折衷を作ってきています。ですから輸出のルートといいますか、きちんと情報を発信することはとても大事なことですね。
- 中村
- そうした意味でこの「世界料理サミット2009」が日本の食文化を世界に発信する絶好の機会になればと思います。
- 服部
- 開催まであと少しです。引き続きご協力をお願いいたします。
- 2025.06.01
- 第20回 食育推進全国大会 in TOKUSHIMA開催!
- 2025.05.25
- 第30回ハットリ・キッズ・食育・クッキングコンテストを開催!
- 2025.02.02
- 第67回HATTORI学園祭